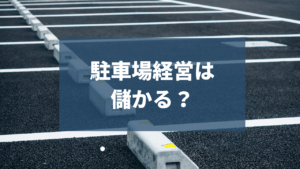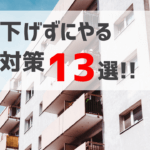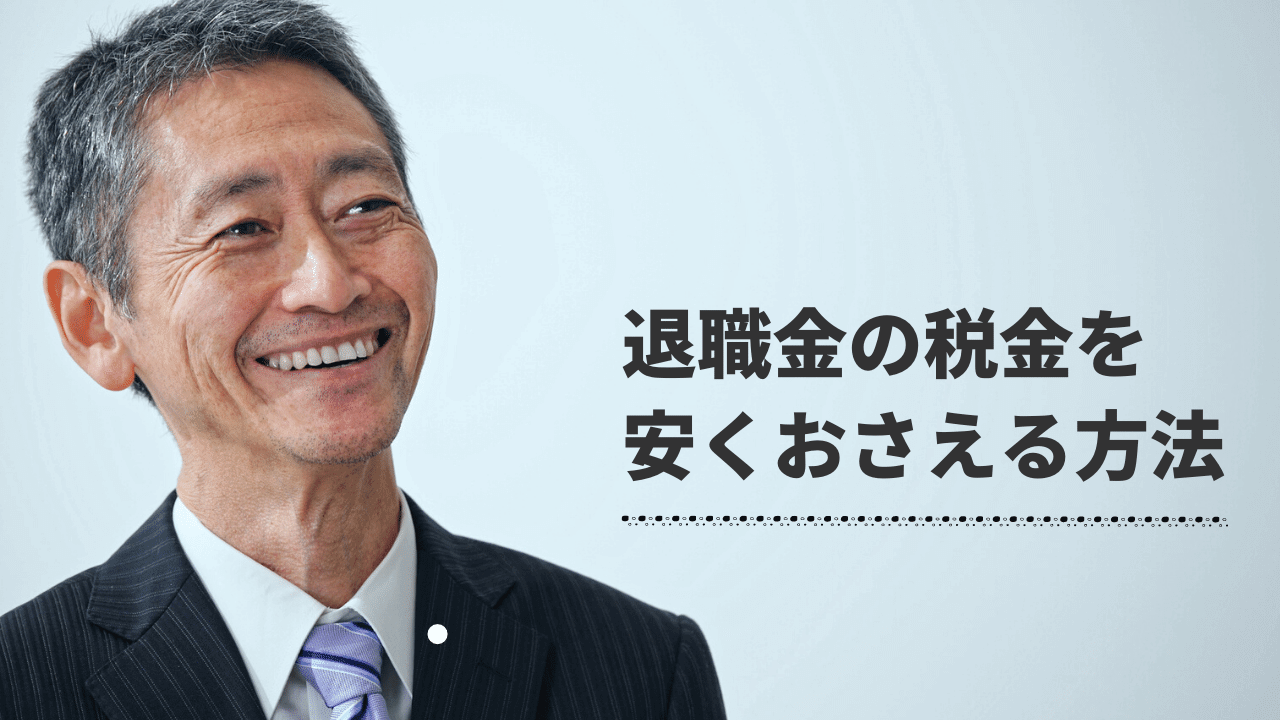
「退職金が支給されたけれど、所得税や住民税が高いと聞いたことがある…」
「他の人達は退職金をどれぐらい貰っていて、税金をどれぐらい支払っているのかな…」
こんなふうに、退職金の税金について不安や疑問を抱えている人はいませんか?
自分で退職金にかかる税金額を計算できるようになれば、税金分の退職金を残しておくことができ、税金の支払いに慌てずに済みます。
そのため、退職金にかかる所得税や住民税の計算方法を覚えておきましょう。
退職金を受け取った翌年の税金について

退職金を受け取った場合は、課税退職所得金額に応じた所得税と住民税を支払わなければいけません。実際に、退職金を受け取った翌年は、どれぐらいの税金を納めなければいけないのでしょうか?
納税金額を把握しておくことで、納税に備えることができます。そのため、退職金を受け取った翌年の税金額を自分で計算できるようにしておきましょう。
退職金を受け取った翌年の税金の計算方法
1. 退職所得控除額を計算する
まずは、退職所得控除額を計算します。控除額は勤続年数に応じて計算方法が変わります。
| 勤続年数20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円) |
| 勤続年数20年以上の場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20) |
※勤続年数は端数分は切り上げます。
2. 課税退職所得金額を計算する
退職所得控除額を差し引いて、課税退職所得金額を計算します。
(退職手当額―退職所得控除額)÷2=課税退職所得金額
3. 所得税の計算をする
課税所得金額から所得税を計算します。
課税退職所得金額×所得税の税率―控除額=所得税額
※復興特別所得税=基準所得税額×2.1%が加算されます。
| 課税退職所得金額 | 税額 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0万円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 9.75万円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 42.75万円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 63.6万円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 153.6万円 |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 279.6万円 |
| 4,000万円超 | 45% | 479.6万円 |
4. 住民税の計算をする
課税所得金額から住民税を計算します。住民税は市町村民税と都道府県民税の2種類の税金を納めなくてはいけません。
市町村民税=課税退職所得金額×6%
都道府県民税=課税退職所得金額×4%
事例:勤続年数25年で退職金2,000万円の場合
実際に、退職金をもらった翌年の税金を計算してみましょう。
- 退職所得控除額=800万円+70万円×(25-20)=1,150万円
- 課税退職所得金額=(2,000―1,150)÷2=425万円
- 所得税=425万円×20%-42.75万円=42.25万円
- 復興特別所得税=42.25万円×2.1%=0.88万円
- 住民税=(425万円×6%)+(425万円×4%)=42.5万円
上記の計算式により、所得税42.25万円、住民税42.5万円が退職金から差し引かれることになります。
所得税や住民税の支払い時期
所得税に関しては、会社側が退職金から差し引いてくれるため問題がありません。しかし、住民税は自分で納付しなければいけません。住民税の納付書は、毎年6月上旬に前年度の所得に応じた税額の納付書が送られてきます。
通常の住民税の納税額よりも高くなるため、退職金を全て使用せずに住民税分は必ず管理しておきましょう。
退職金を全て使用してしまい、納税ができないという方もいるため注意してください。
退職金にかかる税金を安く抑える方法

退職金にかかる税金には優遇措置が用意されています。優遇措置を受けるための手続きを忘れずに行い、税金を安く抑えましょう。ここでは、退職金にかかる税金を安く抑える方法をご紹介します。
退職所得の受給に関する申告書を提出する
退職一時金には、課税される税金額が1/2になる優遇措置が用意されています。この優遇措置を受けるために、会社側に退職所得の受給に関する申告書を必ず提出してください。この申告書の提出を忘れてしまうと、退職金の総額20%に所得税がかかってしまうので、注意しなければいけません。
退職所得控除を適用して税額計算する
退職金を受け取ると、一時的に高額な収入を得ることになります。このまま給与と同じように所得として計上すると、所得税率が高くなってしまうため、退職所得控除を適用して税額を計算してください。退職所得控除を適用することによって、大きく税金が軽減されます。
補足:提出し忘れた場合は確定申告をしよう
退職する際に、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと慌てている方もいるかもしれません。しかし、ご安心ください。会社に申告書の提出を忘れた場合、確定申告をすれば、納めた税金は還付されます。しかし、確定申告は手間がかかるため、退職時に申告書を忘れずに提出することをおすすめします。
退職金についてよくある質問

退職金にかかる税金について理解をしたところで、退職金に関して良くある質問についても確認しておきましょう。
Q.会社員が貰える退職金の相場はどれぐらい?
他の人の退職金事情はデリケートな話なので聴くことはできないですが、とても気になっている人は多いです。厚生労働省が公表している「就労条件総合調査結果の概要」によると退職金は下記の通りのようです。
- 定年退職の場合:1,941万円
- 自己都合退職の場合:1,586万円
- 早期優遇制度を利用した退職をした場合:1,966万円
参考資料:厚生労働省「就労条件総合調査結果の概要」
上記の金額は、新卒から定年まで勤務した方の平均退職金額です。勤続年数によって退職金額は変動します。また、30人以上の従業員がいる企業で、退職金を用意していない企業の割合は19.5%となっているため、多くの企業で退職金制度が設けられているのが現状です。
Q.退職金を貰ったときの源泉徴収票は必要?
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば、退職金にかかる税金は会社側が計算して徴収してくれます。そのため、受け取った厳選徴収票が必要になることはありません。しかし、年初めに退職をした場合や通常の賞与のように退職金が支給された場合は確定申告が必要となるので、厳選徴収票は大切に保管しておきましょう。
Q.退職金を受け取ったら確定申告は必要?
会社側が、退職金にかかる所得税や住民税を計算してくれるため、一般的には確定申告の必要はありません。しかし、他の不動産所得・事業所得がある場合は、確定申告しましょう。
まとめ
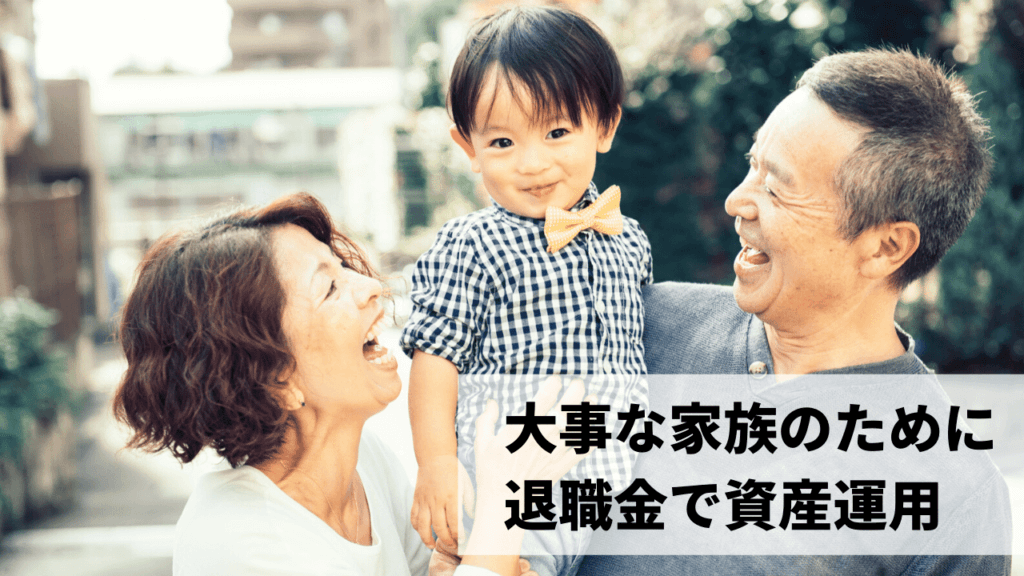
退職金には、所得税と住民税がかかります。所得税は、会社側が退職金から差し引いてくれますが、住民税は自分で納付しなければいけません。翌年6月に納付書が送られてきますが、非常に高額な金額となります。そのため、住民税分の退職金は使わずに貯めておきましょう。
また、退職金を受け取ったら、資産運用方法を考えてみるのはいかがでしょうか?老後100年時代となっているため、定期的に家賃収入が得られて、年金保険の代わりになる不動産投資が人気を集めています。
2,000万円を現金で持っていれば、毎月10万円ずつ使えば、16年で使い終わってしまいます。しかし、不動産投資であれば、不動産所有している限り、家賃収入が見込めるのです。
ぜひ、不動産投資セミナーで情報収集をして退職金の資産運用方法として検討してみてください。